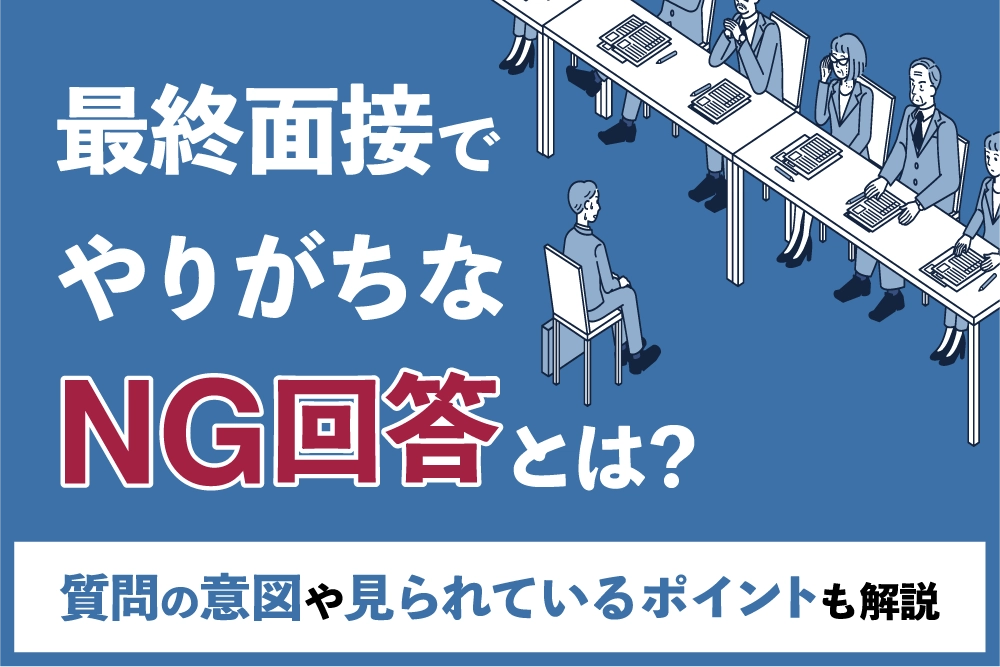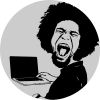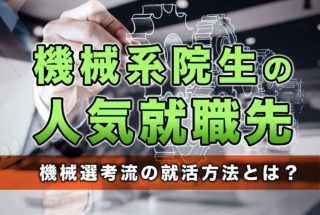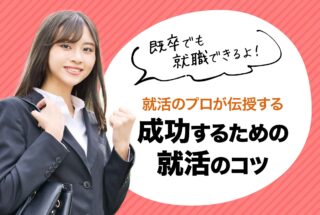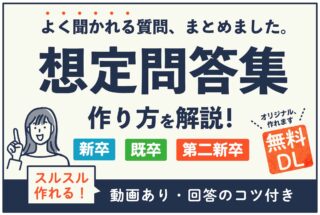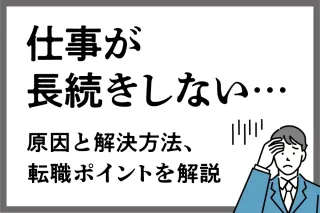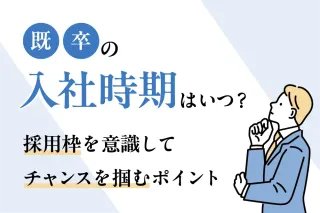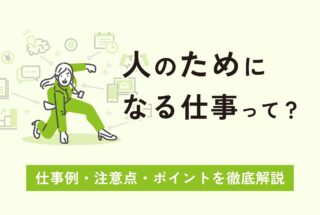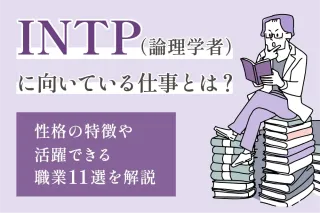せっかく最終面接まで進んだのなら、すんなり内定獲得したいですよね。
しかし、最終面接でも落ちる人がいるのは事実です。
この記事では、人材支援会社UZUZの代表、岡本啓毅氏による解説動画を元に最終面接で落ちる人の特徴を解説していきます。
対策も解説しているので、合わせて確認して最終面接の通過率を上げていきましょう。
きっと、内定を獲得するための参考になるはずです。
▼この記事の元になった動画はこちら
この記事の監修者

岡本啓毅
YouTube「ひろさんチャンネル」運営 / 株式会社UZUZ 代表取締役
北海道出身。第二の就活を運営する「株式会社UZUZ」を立ち上げ、数多くの就職をサポート。“自らと若者がウズウズ働ける世の中をつくる”をミッションに、YouTubeでは「就職・転職で使えるノウハウ」を発信中。X、TikTokなどSNS等の累計フォロワー数は13万人を超える。
正社員求人多数!
あなたのキャリアを
UZUZが徹底サポート
- すべて完全無料!
- 安心!優良企業のみ紹介
- あなた専用!寄り添ったキャリア支援
そもそも最終面接で面接官は何を見ているのか
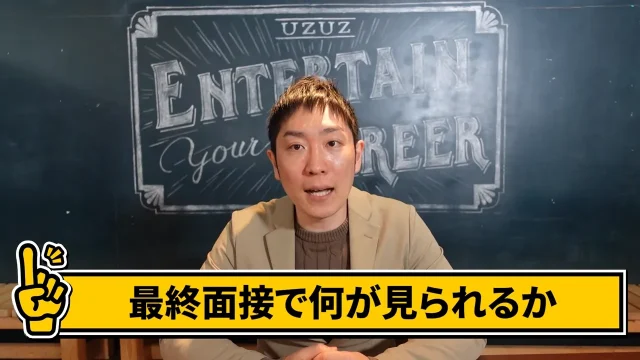
最終面接で落ちる人の特徴を確認する前に、まずは最終面接では何が見られているのかを知っておきましょう。
結論、最終面接だからといって、特別な視点で見られることは少ないです。
基本的にこれまでの面接で見られてきた個所と、さほど変わることはありません。
すなわち、最終面接で面接官がよく見ているのは「入社後に活躍してくれそうかどうか」と「志望度の高さ」です。
そのため、あなたの入社意欲が本当に高いのであれば「御社が第一志望です。内定をいただけたら承諾します」と、しっかり伝えきるとよいでしょう。
監修者コメント

岡本啓毅HIROKI OKAMOTO
最終面接の通過率は会社の選考回数も影響する
最終面接の通過率がどの程度なのか、気になる方もいるのではないでしょうか。
たとえば、「意思確認だけで最終面接まで進めばほとんど通過できる」のか、「最終面接の通過率は50%なのか」など。
結論、最終面接の通過率は、会社によって異なるため、ここで明言することはできません。
しかし、面接回数の違いによって、一定の傾向があります。
一般的には、「面接回数が多い会社ほど、最終面接の通過率は高い」です。
なぜなら面接回数が多い会社の場合、それまでの面接で十分に選考は済んでいるので、役職者へ顔見せをするだけだったり、最終的な入社の意思確認だけだったりするため、通過率が高いのです。
一方で、面接回数が少ない場合は、最終面接もしっかりと「選考」が行われるので、通過率が低くなりやすい傾向があります。
とはいえ、面接回数に関わらず、最終面接は気を引き締めて臨むようにしましょう。
最終面接で落ちる人の回答と対策|よくある質問別に解説!
ここからは、最終面接で聞かれることが多い質問を取り上げ、それに対する落ちる人の回答の特徴を紹介していきます。
それぞれ、落ちないための対策も解説していくので、合わせて確認していきましょう。
1.「入社後にやりたいこと」の落ちる回答と対策
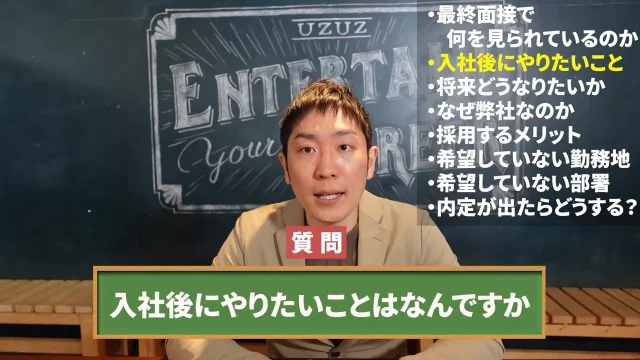
1つ目は、「入社後にやりたいこと」への回答です。
この質問では、入社後に「本人のやりたいこと」と「会社側が任せたい仕事が一致」しているかどうかの確認が行われている場合が多いです。
一致していれば活躍してくれる可能性が高そうと判断できるため、ズレがないかどうかをチェックしようとしています。
- 直近の配属先では“できないこと”をやりたいと、伝えてしまう
- その会社では実現できない事柄をやりたいこと、と伝えてしまう
上記のような回答をしてしまうと、採用してもすぐに希望を叶えることができないため、「他社に採用されたほうがお互いのためではないか?」と思われてしまいやすいです。
- 配属先でできることの範囲から、やりたいことを伝える
あなたが応募している職種の仕事内容や初期配属先などは、調べたり聞いたりしてみれば事前に分かるはずです。
その会社で、初期に実現しやすいことの範囲内で、やりたいことを答えるようにしましょう。
監修者コメント

岡本啓毅HIROKI OKAMOTO
希望を優先するのか、入社を優先するのかバランスを考えておこう
「やりたいこと」を考える際に大事なのは、やりたいことを優先するのか、それともその会社に入社することを優先するのか、どちらを重要視するかです。
例えば「総合職採用」では、希望する配属先に配属されるかどうかは分かりません。
たとえば、営業チームに配属される可能性が高い会社であるなか、自分の希望としては、「広報をやりたい」と考えているとします。
自分がやりたいことを優先するなら、「広報をやりたい」と伝えてもよいでしょう。
配属後、広報になれるかどうかは分かりませんが、将来的に広報に異動できる可能性もありますし、自分の意志を貫いた就職活動ができます。
ただし、「広報としてやりたいこと」を伝えてお見送りになるなら、それは仕方がないことだ、と割り切れるかどうかは重要です。
就職活動では、会社側が「こう答えてほしい」と思っていることを想像して回答することで、採用されやすくなる傾向にあります。
入社できることを優先するのであれば、あえて広報に関しては触れない選択肢もあるのです。
選考で様々な質問に答えると思いますが、その際は希望を優先するか、それとも入社できることを優先するのか、バランスを考えながら回答するようにしましょう。
2.「将来どうなりたいか」の落ちる回答と対策
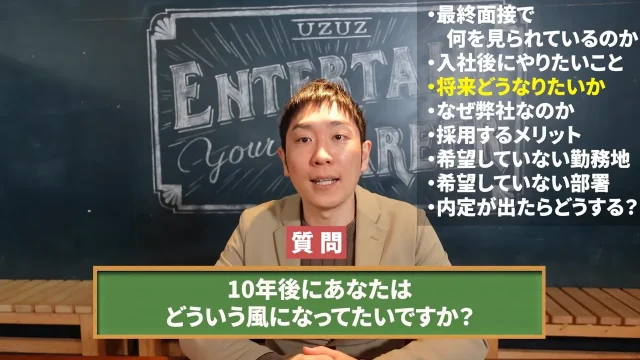
2つ目は、「将来どうなりたいか」への回答についてです。
「10年後・5年後どうなっていたいか」と聞かれることもありますが、同じ内容の質問だと思っていいでしょう。
この質問の意図は、「入社後にどうなりたいのか」の確認です。
「本人のやりたいこと」と「会社が任せたい仕事」のミスマッチを防ぐとともに、どんなキャリアを描き、どんな活躍をしてくれるのかを確認しているのです。
- 独立や転職など、その会社から離れることを伝えてしまう
将来的には「起業したい」「フリーランスになりたい」、「より良い会社に転職したい」と考えている人もいるでしょう。
たとえ、それが本音だったとしても、会社は長く在籍して活躍してほしいと考えています。
そのため、離職を前提としてアピールしてしまうと、会社側の希望とズレてしまうのでお見送りになる可能性が高まります。
- その会社を辞める可能性があっても伝えない
- どんなキャリアを築きたいか(辞める前提なら、その直前でどんな状態になっていたいか)を伝える(例:マネージャーになる、売上トップになる)
起業や転職を念頭に置いていたとしても、「ここまで能力を身につけたら独立する」「ここまで職位が上がったら転職する」という基準は考えているのではないでしょうか。
起業などが前提の人は、会社を辞める判断ができる直前の状態でどうなりたいかを「将来どうなりたいか」の理想像として伝える方法がおすすめです。
ただし、起業や独立を歓迎している社風の会社であれば、「起業したい」といった想いを伝えても問題ありませんよ!
3.「なぜ弊社を志望するのか」への落ちる回答と対策
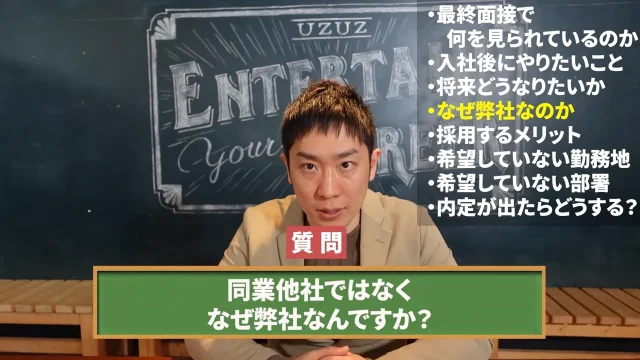
3つ目は「なぜ弊社を志望するのか」への回答についてです。
この質問の意図は、「本当に自社を志望しているのか?」という志望度の高さを確認することにあります。
なぜ同業や競合他社ではダメなのかという理由を聞いている、と言い換えてもいいかもしれませんね。
質問に答えるためには、同業他社や業界全体の調査を行う必要があります。
- 誤った差別化ポイントを答えてしまう
- 業界内での他社との違いを答えられない
上記のように答えてしまうと、しっかり業界を調査していないことがバレてしまい、志望度の高さが疑われてしまいます。
その結果、「弊社じゃなくてもいいのでは?」と思われて落ちる可能性が高まるのです。
- 志望企業も含めた同業他社を調べておく
- 業界内での志望企業の立ち位置と特異性を調べる
調査を行い、他社と応募企業の明確な違いをはっきりと伝えることで「よく調べてきているな」「だから弊社が良いのか、志望度も高いな」と感じてもらえます。
ただ、調査をしてみて、「あまり同業他社と大きな違いがない」という場合もあるかもしれません。
他社と明確な違いがない場合のテクニックは、「人」で差別化することです。
たとえば、「説明会や面接でお会いした、御社の社員さんには〇〇という魅力があると感じています」のように、他社では感じられない「人」を起点とした違いを伝える方法です。
4.「あなたを採用するメリットは何か」への落ちる回答と対策
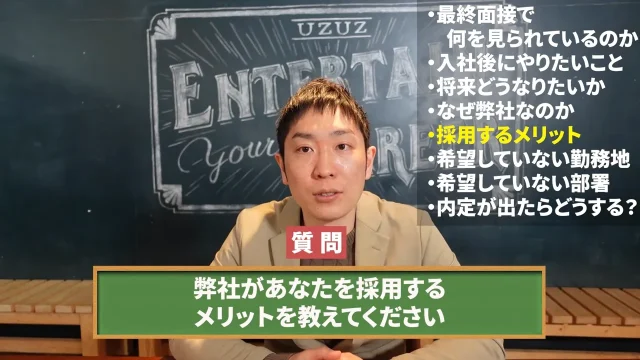
4つ目は「あなたを採用するメリットは何か」についての回答です。
この質問の意図は、仕事内容をしっかり調べているかどうかを確認することにあります。
- 会社から求められる役割とズレたことを言ってしまう
働いた経験がないのに、メリットを聞かれても分からないよ、と思うかもしれませんね。
しかし、会社が求めている役割からズレたことを答えてしまうと、職種理解ができていない(職種を調べてきていない)と感じられて、志望度の高さを疑われてしまいます。
- 仕事に求められる「成果」に対して自分が与えられるポジティブな影響を答える
- 受けている職種で活躍している人材の特徴を調べ、その特徴と合致している自身の要素を伝える
職種を調査するときは、輝かしい面だけでなく、地道な努力が必要な面も、しっかりと調べるようにしましょう。
でないと、面接官の意図を汲み取った回答をすることができません。
職種の特徴をしっかりと調査し、「〇〇という経験があるので、この職種の△△に役に立つと思います」と具体的に伝えるようにしましょう。
そうすれば、職種への調査状況から志望度の高さを感じてもらうことができ、採用するメリットも伝わるので、落ちる可能性を減らせます。
5.「希望していない勤務地に配属されたらどうするか」への落ちる回答と対策
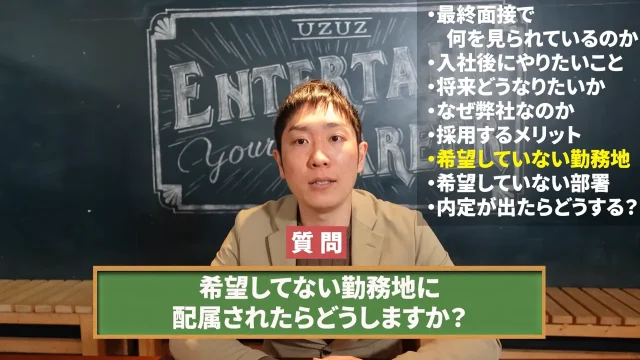
5つ目は、「希望していない勤務地に配属されたらどうするか」に関する回答です。
質問の意図は言葉通り、勤務地の希望に添えなかったときにどう思うかを知りたいから聞いています。
- 本当は勤務地の希望があるのに、嘘をついて「大丈夫だ」と伝えてしまう
本心から「全国のどこでもいい」と思っている人は、自信を持ってそう伝えましょう。
しかし、多くの人にとってどこに住むかは重要なことだと思います。
様々な都合で勤務地を限定したい人も多いのではないでしょうか。
全国展開している企業の場合は、全国転勤が必要なケースが多いので、この質問をされる可能性は高いと思います。
よくあるのが、希望勤務地の候補を複数提示しなければならず、本当は希望勤務地は1か所しかないにも関わらず第3希望まで書いたところ、第1希望が通らないことです。
「第1希望の勤務地以外では働きたくない」という人のなかには、内定後・入社後に、勤務地を理由に早期離職(または内定を蹴る)して、既卒になるケースも珍しくありません。
- 転勤が大丈夫なら「問題ないです。その場所で新しい出会いがあると思います。前向きにやっていきたいです。」と伝える
- 勤務地にこだわりがあるなら、正直に「◯◯のため、◯◯の地域で働きたい」と伝える
場合によっては、「希望勤務地が通らないのであれば辞退します。希望勤務地が通る企業で働きたいです」と伝えてしまうのも良いでしょう。
全国転勤がある会社では、いわゆる「勤務地ガチャ」は起こり得ます。
それがイヤなら、そもそも全国転勤のある会社は受けない、勤務地の希望が通らない会社は受けない、正直に「希望勤務地でないなら御社では働けません」と伝えるようにしましょう。
入社後にミスマッチとなってしまうと、早期退職につながりかねません。
よく考えて、回答するようにしましょう。
6.「希望していない部署や配属先になったらどうするか」への落ちる回答と対策
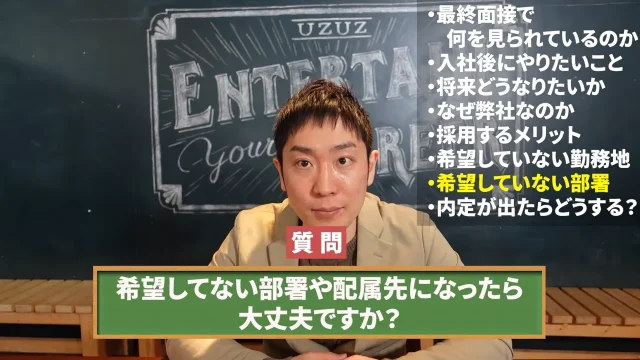
6つ目は「希望していない部署や配属先になったらどうするか」についての回答です。
これは総合職採用のときに聞かれることが多い質問です。
総合職として入社し、研修後に適性を見ながら配属先が決められることになりますが、人事は配属後に辞めてほしくないと考えています。
質問の意図は、そうならないかどうかを確認するために聞いています。
- 希望職種があるのに「どこに配属されても大丈夫です」と答えてしまう
これは、総合職採用でよくいわれる「配属先ガチャ」のことです。
「この部署で働きたい!」という強い希望があるにも関わらず、全く異なる部署に配属されてしまうと、ミスマッチを感じて早期退職につながりかねません。
- とくに問題がないのなら「大丈夫です」と伝える
- 総合職採用で受けている以上、起こり得ることなので受け入れる、と伝える
- あえて「希望職種に配属されないなら辞退する」と伝える
こだわりが強い場合、落ちる可能性が高まることを承知の上で、あえて「希望職種以外に配属されるなら辞退する」と伝えてしまうのも手ではあります。
それを伝えたうえで内定をもらえた場合、希望職種に配属される可能性が高いためです。
一方で、希望の職種になれないことは総合職採用にはつきものですし、働き続けていると不本意な異動を命令される可能性もあります。
そのため、「どこに配属されても適応できる適応力や対応力を鍛えよう」と割り切って、受け入れてしまうのも一つの手段です。
その会社に入ることが優先なら、「希望部署でなくても学びがあるはずだ」とポジティブに思考を転換するのも良いでしょう。
7.「弊社から内定が出たらどうするか」への落ちる回答と対策
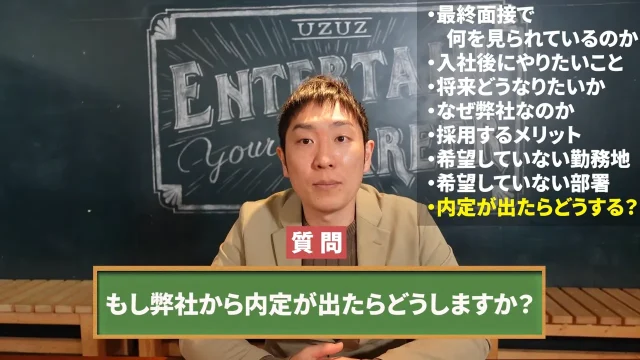
7つ目は「弊社から内定が出たらどうするか」についての回答です。
各社の採用には、採用する人数の目標があります。
ある人に内定を出すということは、別の人はお見送りをしているということでもあります。
内定を出したのに辞退されると採用計画に影響が出てしまうので、なるべく内定を出した人には入社してほしいと考えています。
この質問の意図は、単純に内定を出したら承諾して入社してくれるかを知ることです。
- 入社をにごす回答をする
- 入社意思がないにも関わらず「入社する」と答えてしまう
会社からの評価が高い場合は、他社の選考結果が出るまで待ってもらえる場合もあります。
ですが、入社をにごす回答をすると、落ちる可能性が高まる傾向にあるので気をつけたいところです。
一方で、入社する意志がないにも関わらず「入社する」と答えることも避けるようにしましょう。
入社する企業は別の会社になると思いますが、同業界であれば意外と人のつながりがあったり人事同士がやりとりをしていたりと、情報は伝わってしまうものです。
内定承諾の段階で嘘をつくと、後々自分の身に返ってくるかもしれません。
- 志望度が高いなら、「入社します」と伝える
- 入社意志がそれほど固まっていないなら、素直に「考え中である」と伝える
ここでできることは、志望度が高いなら入社の意志を伝えること、そうでないなら正直に「考え中です」「他社の状況も合わせて考えています」と答えることだけです。
本当に入社意志が強いのであれば、表情や話し方などで真剣さが伝わるようにすれば、なお良いでしょう。
まとめ
最終面接で落ちる人の特徴・対策をしっかり覚えて、内定獲得のために活用していきましょう!
最終面接を突破するためには、この他にも様々なテクニックがあります。
もし、さらに深く最終面接への対策を知りたいのであれば、私たちUZUZが運営する無料の就職エージェントサービスにご連絡ください。
就職エージェントサービスとは、キャリア相談や求人紹介、そして最終面接を含む選考対策を無料で受けられるサービスのことです。
私たちはこれまで6万人以上の就職・転職をサポートしてきており、その過程で蓄積してきた数多くの選考対策ノウハウをお伝えできます。
最終面接を控えている方、自分の面接対策が問題ないか心配な方は、ぜひ一度ご連絡ください。
正社員求人多数!
あなたのキャリアを
UZUZが徹底サポート
- すべて完全無料!
- 安心!優良企業のみ紹介
- あなた専用!寄り添ったキャリア支援